- 2024/03/25 メディア掲載情報
- 2024/03/13 新規相談受付を再開いたします。
- 実在する弁護士名をかたった「なりすまし詐欺」にご注意ください
- ホームページをリニューアルしました
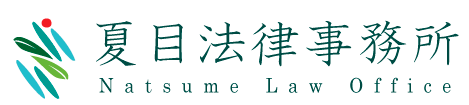
042-767-2592
受付時間:平日9:00 ~17:00(12:00~13:00を除く)
住所:〒252-0303 神奈川県相模原市南区 相模大野3丁目10-1
ライオンズマンション相模大野901
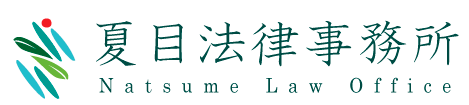
042-767-2592
受付時間:平日9:00 ~17:00(12:00~13:00を除く)
住所:〒252-0303 神奈川県相模原市南区 相模大野3丁目10-1
ライオンズマンション相模大野901


| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 13:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |

当事務所は、
1.御依頼者の立場にたって物事を考え、
課された状況下で経済的利益の最大化を図ること
2.御依頼者のお話をしっかりとうかがうこと
3.御依頼者の精神的な負担に着目し、その軽減に努めること
の3点を大切にし、業務を行っています。
様々なITの媒体の発展に伴い、弁護士も御利用者様から選ばれる時代になりました。
当事務所は、常々、お越しいただいた方に対して、選ばれた気持ちを忘れずに、それに相応しい気持ちでお応えしたいと考えています。
当事務所は、事務所にお越しになるすべての方の御相談を始め、御案件の終結に至るまで夏目弁護士が担当します。御相談内容について、一方的に方針を決定するのではなく、お一人お一人にとって何が最善であるのかを考え、出来る限り密に打ち合わせを行い、目指す方向性を共有しながら共に事件処理を進めて参りたいと考えます。
事務所へお越しの際にも、プライバシーへの配慮と同時に打ち合わせや御相談に伴う精神的なご負担を軽減すべく、完全個室で御相談をさせていただきます。
夏目弁護士は、家族の交通事故がきっかけで弁護士を志し、弁護士登録以後10年以上、交通事故等の一般民事事件処理に注力してきました。交通事故を始めとする法的問題でお悩みの方は是非一度当事務所にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
詳しい弁護士プロフィールはこちら
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 13:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
 当事務所は、交通事故問題に注力して取り組んでおります。 これまで多数の解決実績が集積されております。
当事務所は、交通事故問題に注力して取り組んでおります。 これまで多数の解決実績が集積されております。
もっと見る
 遺産分割協議を始めとした相続分野の問題について、協議・調停・審判等の各分野で多数ご依頼をいただいております。相続人間での紛争性の有無を問わず御依頼いただけます。
遺産分割協議を始めとした相続分野の問題について、協議・調停・審判等の各分野で多数ご依頼をいただいております。相続人間での紛争性の有無を問わず御依頼いただけます。
もっと見る
 不貞の慰謝料請求など離婚問題に代表される男女の法的トラブルについて、協議・調停・訴訟等の各分野で多数ご依頼をいただいております。
不貞の慰謝料請求など離婚問題に代表される男女の法的トラブルについて、協議・調停・訴訟等の各分野で多数ご依頼をいただいております。
もっと見る
 破産や任意整理等、債務整理の分野についても多数御依頼いただいております。
破産や任意整理等、債務整理の分野についても多数御依頼いただいております。
もっと見る
 法人の方は事業者向けプランとして「法律顧問契約」をご利用いただけます。月額の費用は掛かりますが、それを上回るメリットやサービスをご提供できるものと考えています。
法人の方は事業者向けプランとして「法律顧問契約」をご利用いただけます。月額の費用は掛かりますが、それを上回るメリットやサービスをご提供できるものと考えています。
もっと見る
交通事故・離婚(男女問題)・相続・債務整理は
初回相談料無料!
まずはお電話もしくは当ホームページのお問い合わせフォームから相談予約の申し込みをお願い致します。
TEL: 042-767-2592【受付時間平日9:00~12:00/13:00~17:00】
● 交通事故・離婚(男女問題)・相続・債務整理は初回法律相談料無料とさせていただいております。
事件の種別によっては有料相談となる場合がございますので、事前にお問い合わせ下さい。
● 御相談の際には、事件に関係するとされる資料をお持ちいただきますとスムーズに御相談が進みます。
● 初回相談時に方針の決定が困難な場合は、継続相談とさせていただく場合があります。
● 合わせて事件をお引き受けできるかどうかの検討を致します。
● 事件をお引き受けできる場合、ご要望に応じて費用のお見積りを致します。
● 方針と費用を考慮いただき、依頼についてご検討ください。
● 契約時には、お認印をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
● 契約書等を取り交わし、委任状を頂戴いたします。
速やかに業務に着手致します。
御依頼者様と随時ご連絡を取りながら進めてまいりますので安心してご依頼ください。
●入口での検温にご協力ください。
●使い捨てのスリッパをご用意しております。
(画像とは異なります。)
●相談室にはパーテーションを設置しております。
●お出しするお茶はペットボトルをご用意しております。
●相談時のマスク着用にご協力いただいております。
(マスクをお持ちでない場合には、弊所にてマスクのご用意がございます。)



/ 当事務所の利用をご検討いただいた場合、概ね以上の1~6の順に進みますのでご参考下さい。
/ 最短で初回相談日からの業務開始が可能です。
042-767-2592
受付時間:平日9:00 ~17:00
(12:00~13:00を除く)
当サイトはSSL暗号化通信を使用しています
Copyright © 夏目法律事務所 All Rights Reserved.